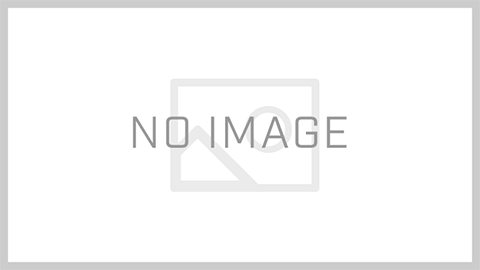本当に面白い作品は、必ずパロディを生むか否か
先日、Twitterで気になる話題が流れてきた。
概要としては「本当に面白い作品は、必ずパロディを生む」と言う岡田斗司夫さんの発言に対して、名指しされた芸人で絵本作家のキングコングの西野さんが「雑な評論」と言い、そこに2チャンネル創始者のひろゆきさんが「メディアミックスを多くやると、二次創作が生まれづらくなるの法則がある気がする」と独自の分析を被せる、と言った内容だ。
気になったので、じゃあ、どういった作品が二次創作を作られるのか、また、面白くても二次創作を作られないなら、その原因はどこにあるのかを、ゆるく軽く調べてみたく思い、ノリと勢いで記事を書き始める。